 ..
..広告ですよ。(クリックしてもらっても別にお金は入りませんが。)
 .. .. |
広告ですよ。(クリックしてもらっても別にお金は入りませんが。) |
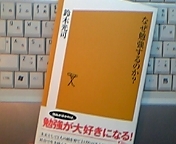
何で勉強するのかしらね。
また本を読んでいます。
今日は、鈴木光司さんの「なぜ勉強するのか」という本。
自分を含め、人間って、何で勉強するのかしらね。
答えは人それぞれかと思いますが、私は常に勉強とは
「自分の世界を広げるためのモノ」
だと思っています。
で、世界を何で広げなきゃ行けないの?という理由については、
「人生を豊かにして、しやわせになるためのモノ」
だと思っています。
一般論に近いですけど、私は人生とはそう言うもんだ、
そういう目的を持っているものだ、と思っています。
もしこれが戦争で非常に荒れた国だったらこういう答えには
ならないんですけれども、幸いなことに、明日の食料や住居、
お金などの心配が今のところそんなに問題にはならない今日の
日本に住んでいる私としては、幸せになることが、人生に対する
シンプルな答えであり目的なのだろう、と。
人間どうせ死ぬのに幸せを求める。ただ栄養を摂っていれば
それなりに生きては行けるのに、人間は様々な活動をし、
様々な経験をし、いろんなことを学んで、人生の糧としていく。
人生の糧は、幸せになるための材料として使われる・・・。
言うなれば、フィジカルな糧と共に、メンタルな(イモーショナルな)
糧も必要とし、その両者でもって人とは生を得ているのだという訳です。
さて、生きるのに学ぶことが大事っぽいというのは何となく
分かるものの、なぜ学ぶことがこんなに義務的に感じるのでしょうか。
例えば勉強って言っても、狭義な「学校で学ぶ知識」を取り上げれば、
私も学生時代は義務としか考えていませんでしたし、毎週ある単語テストや
毎月ある実力テストなんかには、拒否感を覚えるほどでした。
しかも、卒業して、社会に出た今、学校で学んだ知識が人生の直接的な
糧となっているかというとそうではなくて、「そりゃ、学校で
学んだところで、すぐには幸せにはなれないよ」と、いうのが実感です。
例えば数学で微分や積分を学びましたが、それで今の私の人生が
薔薇色になった、とはあまり感じられません。
じゃ、勉強っていらないものなの?というと、そうでもない。
学ぶことを、広義で言うところの「経験の蓄積」であると考えた場合、
これこそが勉強の意義であり意味であると思うわけで、社会に出て
自分自身で生きていくときに初めて武器・道具たるものなのだと
言うことができます。
本日読んでいるこの本も、まぁそんな内容をまとめている本でして。
氏はこの本の冒頭で、
・学校で学ぶ知識そのものは、社会に出てからすべてが
役に立つとは言えない。
・しかし、学ぶ方法を学ぶことがきわめて重要なのであり、
学校では方法と経験を教える/学ぶという意識が必要だ
・よって、勉強には必ず理由があるし、「学校では社会で役立つ
ことを教えてくれなかった」なんていう大人は間違っている
・そして、子供(学ぶ者)に、学ぶ理由や動機を端的に示してあげる
必要がある
ということを述べています。
私もそういったアプローチには賛成というか、これまでも
そうやって考えてやってきたんですが、一つ付け加えるとすれば
学ぶ理由や動機と共に、その先にあるもの、つまり夢や希望、
理想的な姿などを学習者に見せてあげて、その実現の道具として
学ぶことが必要なんだよ、ということを示す必要があると思います。
あくまでも手段である「学び」を、目的(ゴール)にしない、
ということです。
「問と答えが近くなって久しい」なんてよく言いますけれども、
たしかに、効率よく学ぶことを前提にしてしまったがために
知識や経験のコンポーネント化が進んでいることが原因の一つでは
ないかと思います。
これについてはこう、それについてはそう、あれについてはあれ、
と、個別のコンポーネントは理解できても、それを組み合わせて
新たなものを生み出したり、変化させたりすることが不足している
ように思えてならないのです。つまり、学びが手段ではなく
目的化しているということなのです。それを使って、その先
どうやねん、と。そこがゴールじゃねえのか、ということでして。
これに対して鈴木氏は、学習とは「理解力・想像力・表現力 の
3つの力をつけることが重要なのだ」と言っています。
言い換えれば、いかにインプットを理解し、それをプロセスし、
アウトプットするか、ということです。このプロセスの段階で、
プロセッサーなりの解釈や意図が込められ、
アウトプットが多彩化するわけです。
悲しいことに、今の学習では、プロセスまで行かない。
ほとんど、インプットの理解=学習ということになってしまって
います。これでは、人間の多様性・多彩性など求める余地が
一切ありません。なんと学習のつまらないことか!
教える側も、きっと同じことは感じているのでしょう。
しかし、ノルマはあるし、インプットを理解させるだけで精一杯だし、
とてもプロセスまで行かない。行けたらいいけど、時間がない。
時間に見合った結果が出そうにない。そういった「あきらめ」が
あるように思います。結局、アウトプットを評価するのではなく、
インプットを評価せざるを得ないのです。なんと指導の
つまらないことか!
日本の教育再生が話題になっていますが、アレって、なにを
ゴールに見据えているのかしらね。 前のゆとり教育って、
基礎学力の徹底と、詰め込みすぎた点数主義の教育をやめようって
ことだったじゃない。オレ的にはあれは、アウトプットや
プロセスの評価をさらに断念して、インプットの成果を
評価するだけにしちゃった気がして大反対だったんだけど、
今度の見直しは、何をするんだろうか。 週休二日を学校や
自治体の判断で変更できたりするっていうのは聞いたけど、
結局ゴールがインプット評価だったら同じだとおもうんだよね。
プロセスとアウトプットを評価できる仕組みを作ってください。
大学がプロセスとアウトプットを評価するのであれば、高校も
プロセスとアウトプットのやり方を学ばせる仕組みを設けてください。
高校がプロセスとアウトプットのやり方を教えるのであれば、
中学校は、その材料となるインプットを学ばせてください。
中学がインプットを行うのであれば、小学校は、インプットの
やり方を学ばせてください。
そうやって、ゴールから戻っていけば、必然的にいまの教育に
足りない所なんて、いくつでも出てくると思うんだけど。
そんなに難しいことなんですかね、教育再生って。
結局ゴールが無いから、「ここは譲れない!」ってところがなくて
妥協に妥協を重ねて、みんなが楽な方にいっちゃってるんじゃ
無いんですかね。政府で決めればイイじゃん。「ここは必須。
これ出来なきゃ、卒業にはしません。」と。その後ろ盾が
あれば、教育って、すんなり行けると思うんだけどなぁ。
出来ないことがまかり通る世の中だからおかしいんですよ。
出来ないことが恥、というのがストッパーになっていた時代は
もう終わったんだから、だったら、出来ないことを抑制する
新たな仕組みが必要なんです。絶対に。
教育、そして現場の教師は、そう言った抑制力がなさすぎる。
努力は大きく評価できるし評価するけど、法律や行政などの
バックアップが一切無いという点で、力がなさ過ぎる。
後ろ盾が無いのに「がんばれ」、なんて易々と言うべきじゃ
無いと思うんだよなぁ。オレ。 教育再生、というんなら、
そういう後ろ盾や土台を固めた上で、教えやすい、そして
学びやすい、今日の現状に合った仕組みを作るべきだと
思うんですが、オレ、生意気言ってますかね。汗
てことで、まとまりが無いので、今日のニッキはこれで終了。
とりあえず、まだ本は途中なので、最後まで読みたいと思います。
(合計150行でした。汗)
| Produced by ふっしぃ |
| E-mail; webmaster@yogore.org |
|
|