 ..
..広告ですよ。(クリックしてもらっても別にお金は入りませんが。)
 .. .. |
広告ですよ。(クリックしてもらっても別にお金は入りませんが。) |
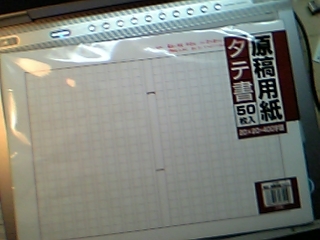
ホントは1週間前にスタートしているはずだった話ですが、小論文を書き始めました。ていうか、予定が1週間ずれて焦っているとはいえ、逆に言えば元々の予定もたった2週間で小論文完成させようとしていたオレの計画もかなりの無茶デスヨネ、とか、風邪が治った頭で冷静に考えてさらに青ざめてみたり。
ま、ごちゃごちゃ言ってても仕方ないので、とりあえず原稿用紙に向かってみる。
が。
書けねえ。気分が乗らねえ。今日は日が悪い。あと、風水的にイマイチ。
とか難癖つけててホントにかけない。
ので、基本に立ち返ると言うことで解説書を読んでみる。
解説書に沿って書いちゃうと「教科書どおりだ!」みたいに、どっちかというとネガティブな(否定的な)感じで怒られちゃうこともあるんだが、まぁ基礎は大切でしょ、ということで。
やっぱり「ベタ」なコトも書いてあるんだけど、所々、印象的なコトもあって。
例えば
・小論文とは、口頭面接と同じものであり、自分の考えを
端的に、かつ理論的に、相手に分かり易く伝えるための物だ。
・序論→本論→結論と、問題提起の部分は論文に不可欠ではあるが
あくまでも自分の論を分かり易く伝えるための方法論でしかない
ことを忘れてはならない。
・論文の書き出しは、問い(テーマ)を改めて自分の言葉で確認し、
その次に問題提起が行われると分かり易い。いきなり問題提起を
してしまうと、まとまりのない論文になりがちである。
とか。
特に、ワタシャ小論文の「書き出し」と「問題提起」と「解決・結論」の組み立てが超絶的に苦手で、こういうニッキ口調とか構成を考えない文章をダラダラと書くことになれてしまっているため、とにかく構成を重視し自分の意見を論理的に述べるっていうのが大の苦手だったりするのだ。
解説書を読んで少し心の霧が晴れたのは、まず小論文は口頭面接と同じだということ。個人的に口頭面接は割と緊張せずすらすらできるので、あぁ、それをそのまま文章に適用すればいいのか、と目から鱗なアドバイスだった。
そして、書き出しにいつも困って5分10分と時間を無駄にしてしまう私だが、書き出しは問われていることを自分なりの言葉で言い換えれば良いんだね。なるほど、とか思って。 いつもそれをすっ飛ばして半歩先くらいのことから書き出すのが正義だと思いこんでいたので、浮ついた文章(というか考えが伝わりにくい文章)になっちゃってたんですが、それを解決する方法は案外単純だったということに気付いたね。
まぁ、分かってても、実際にできるかどうかはまた別問題だから、実践力はまだまだなんだけど。とにかくあと1週間しかないし、できるとこまでやりまさあ。涙
| Produced by ふっしぃ |
| E-mail; webmaster@yogore.org |
|
|